
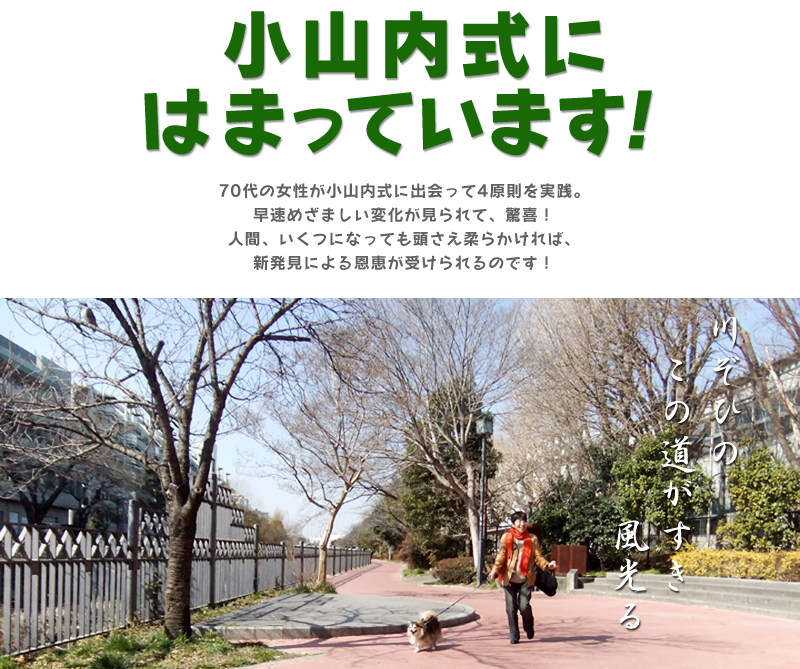
愛犬と散歩する中川さん。
最近、同世代の女性と親しくなり、小山内健康づくりの本を差し上げたところ、ちゃんと読んでくださったうえ、目を丸くして感動された。
小山内式は一般の健康常識と異なるところがあり、敬遠する向きも多いのだが、この方は柔軟な思考の持ち主で、素直に小山内理論を理解され、自分もやってみるという。
はじめて6カ月余りだが、目に見える効果もあらわれて、ますますやる気満々である。
そこで小山内式ビギナーの高齢者代表として、感想を寄せてもらった。
小山内式は一般の健康常識と異なるところがあり、敬遠する向きも多いのだが、この方は柔軟な思考の持ち主で、素直に小山内理論を理解され、自分もやってみるという。
はじめて6カ月余りだが、目に見える効果もあらわれて、ますますやる気満々である。
そこで小山内式ビギナーの高齢者代表として、感想を寄せてもらった。
健康づくりのたのしみが増えた!
中川寛子 (俳人・主婦)
奇妙なおばさんの正体
小山内式健康づくりとの出会いは、まさにカルチャーショックといっていい。
70何年生きてきて、これまで常識と信じて疑わなかったことがひっくり返り、目からウロコが落ちたのだから。
小山内式との出会いによって、私の健康観は大きく修正され、部分的ではあるが、実践により風邪をひかなくなるなど、大いなる恩恵を受けている。
私の人生後半の、ちょっとした事件といっていい、小山内式を巡る顛末をお伝えしよう。
小山内式との出会いは、このサイトを運営する高木亜由子さんとの出会いによる。
私はノエルという名の、チワワとパピヨンとのミックス犬を飼っており、夏は5時頃、冬は懐中電灯を持って6時頃、犬を連れて散歩に出かける。
近くの川の両側が遊歩道になっていて、早朝散歩する常連さんの中に、トロトロと歩くほどのスピードで走る、おばさんともおばあさんともお姉さんともつかぬ、年齢不詳の女性がいた。これが高木さんだった。あとでわかったのだが、このトロトロした走りは「小山内式ゆっくりランニング」によるものらしい
猫が好きらしく、いつも橋のたもとの野良猫に餌やりをしている。動物好きが共通して立ち話をするようになり、ある時ひょんなことから高木さんが編集者をしていらしたことを知った。私も俳句雑誌の編集をしているので、一気に親近感が深まった。
お宅へ伺うようになり、家にはモモタロウという目の大きな猫がいた。そこで小山内式健康づくりに関する本をいただいた。これがはじまりである。
高木さんは小山内理論について情熱を込めて語り、自分は小山内式4原則をすべて実践している。この20年、風邪をひいたことがない。ふとらない。肩こり・腰痛はゼロ。などなど効用をあげられた。
いただいた本を持ち帰って読み、たちまち引き込まれた。どれも読みやすく、説得力があった。専門的なことがらも興味深く読め、高木さんの、小山内理論を広く世に紹介したいという熱意がひしひしと伝わってきた。
2003年に小山内先生が亡くなられた後も、こうして普及活動に力を入れているのもスゴイと思う。
いただいた本は、次の4冊である。読んで強く共感させられたこと、常識をくつがえされたことなどをあげてみる。
 全体を貫くものとして、小山内先生は人間というものを自然の1部としてとらえ、大昔の狩猟採集者としての歴史から説き、動物の生態と比べて描く。それは人間本来のからだのしくみを理解するのに、大いに役立った。
全体を貫くものとして、小山内先生は人間というものを自然の1部としてとらえ、大昔の狩猟採集者としての歴史から説き、動物の生態と比べて描く。それは人間本来のからだのしくみを理解するのに、大いに役立った。
また、生活習慣病というものを、何万年もかかって形成されたからだと、現代生活との矛盾によって生じたものととらえるのも、理解できた。
そのうえで、健康づくりのために提案された4原則を読むと、それほど違和感なく入ってくる。
まずは「朝食抜き」。
私たちは子どもの時から学校では朝ごはんをちゃんと食べてくるよう指導されてきたし、あらゆるメデイアは、「朝食摂取」は健康の源といっている。脳には朝食=健康とインプットされているから、はじめて聞いたときはびっくりした。
しかし小山内先生は、「朝食摂取」はすすめられないといい、野生の生き物を例にとって諄々と説かれる。
狼やライオンは、お腹ぺこぺこの状態で走り回って狩りをして、やっと餌にありつき、食べ終わってから寝る。活動の前に食べるのではなくて、活動が終わってからゆっくり食べる。それがからだのしくみにかなった食べ方という。いわれてみれば、からだと行動と食べ物の関係は、本来そうかもしれない。
そして林業労働者の調査などを通して、激しい労働の前の「朝食摂取」が胃腸をいかに傷つけるか、データを示して説明される。説得力のある事例だ。
私は朝食はとるが、かなりの早起きで、朝飯前に家事や犬の散歩をすませ、つまり活動をしてから朝食を摂るので、正直ホッとした。小山内理論が朝食をすすめないおもな要因は、「食後すぐに活動すると、消化・吸収を妨げて、胃腸を傷つける」というものだから。
風呂上がりに1分間水をかぶれという。
そのこころは、現代人は冷暖房完備の家に住み、飽食暖衣の生活をしているため、からだがなまって抵抗力が落ちている。そこで「水かぶり」という寒冷の刺激を与えて、副腎皮質ホルモンの分泌を促し、免疫力を強めるという。
「水かぶり」によってアレルギーが改善したという、数多くの事例もあげられ、驚かされた。
私は不眠症や腰痛があるほか、とくに健康に問題はない。ただ、風邪をひきやすく、2カ月に1度くらいは38度以上の熱を出し、咳や鼻水に苦しむのが悩みだった。
それで「水かぶり」をやってみようと思った。
とはいえ、全身浴なんてとてもできない。
風呂上がりおそるおそる手足に水シャワーをかけ、少しずつかける範囲を大きくしていった。まだ全身とはいかないが、「水かぶり」の後、手足がポカポカ暖まってくるのは実感できている。その程度だ。
なのに「水かぶり」をはじめて6カ月。なんと私は1度も風邪をひいていない!
「水かぶり」ってすごいと実感した。
高木さんが今世紀に入ってから1度も風邪をひいていないと自慢するのも、うなずけた。
これは週に3回くらい、ゆっくり走って血液循環を良好に維持しようというもの。
よい血液循環は、血圧のコントロールや動脈硬化、がんの予防にもつながるといわれる。
歩くよりも呼吸が弾むくらいの「ゆっくりランニング」のほうが、全身を巡る血液循環の効率がいいとあって、私はノエルとの散歩を、ゆっくり走ることにかえた。といってノエルはオシッコしたり、地面をクンクン嗅ぎまわるので、足踏みすることが多いのだが。
第4の柱「小山内体操」は体幹筋のトレーニングである。これは肩こり・腰痛予防効果が大きいので、是非マスターしたいのだが、まだうまくできない。回数も届かないし、今後の課題である。
といったところで未だ不十分ではあるが、私は小山内式にはまって健康づくりにいそしんでいる。
高木さんは「続けることよ。小山内式は毎日おこなってこそ、不調は改善されるし、健康なからだが維持できる」と励ましてくれる。
そしてパソコンを開いて、当サイトへのある投稿メールを示した。北九州市の女性からのメールで、内容は体操に関する問い合わせだが、次の文が付け加えられていた。
「・・・1昨年より、このサイトで水かぶりを発見して、半信半疑、水かぶりを毎晩するようになって1年、人生最大の悩みであった辛いアトピーがほぼ完治いたしました。気持ちも前向きになり、心から感謝しております
・・・水かぶり健康法が、もっとたくさんのアトピー患者さんに届きますようにと願わずにはいられません・・・」
高木さんはうれしそうに、「こういうメールが来るということは、背後に100人の同じ体験者がいるということなのよ。ゴキブリが1匹出ると、100匹はいるといわれるように」とあまり美しくないたとえを持ち出して、にんまりわらった。
どうやらこうした報告が励みになって、高木さんの活動を支えているようだ。
私もがんばって続けよう。
部分的な「水かぶり」で風邪ひきゼロだから、もう少しあたたかくなって全身「水かぶり」をおこなったら、何が起きるか今から楽しみなことだ。
70何年生きてきて、これまで常識と信じて疑わなかったことがひっくり返り、目からウロコが落ちたのだから。
小山内式との出会いによって、私の健康観は大きく修正され、部分的ではあるが、実践により風邪をひかなくなるなど、大いなる恩恵を受けている。
私の人生後半の、ちょっとした事件といっていい、小山内式を巡る顛末をお伝えしよう。
小山内式との出会いは、このサイトを運営する高木亜由子さんとの出会いによる。
私はノエルという名の、チワワとパピヨンとのミックス犬を飼っており、夏は5時頃、冬は懐中電灯を持って6時頃、犬を連れて散歩に出かける。
近くの川の両側が遊歩道になっていて、早朝散歩する常連さんの中に、トロトロと歩くほどのスピードで走る、おばさんともおばあさんともお姉さんともつかぬ、年齢不詳の女性がいた。これが高木さんだった。あとでわかったのだが、このトロトロした走りは「小山内式ゆっくりランニング」によるものらしい
猫が好きらしく、いつも橋のたもとの野良猫に餌やりをしている。動物好きが共通して立ち話をするようになり、ある時ひょんなことから高木さんが編集者をしていらしたことを知った。私も俳句雑誌の編集をしているので、一気に親近感が深まった。
お宅へ伺うようになり、家にはモモタロウという目の大きな猫がいた。そこで小山内式健康づくりに関する本をいただいた。これがはじまりである。
高木さんは小山内理論について情熱を込めて語り、自分は小山内式4原則をすべて実践している。この20年、風邪をひいたことがない。ふとらない。肩こり・腰痛はゼロ。などなど効用をあげられた。
いただいた本を持ち帰って読み、たちまち引き込まれた。どれも読みやすく、説得力があった。専門的なことがらも興味深く読め、高木さんの、小山内理論を広く世に紹介したいという熱意がひしひしと伝わってきた。
2003年に小山内先生が亡くなられた後も、こうして普及活動に力を入れているのもスゴイと思う。
いただいた本は、次の4冊である。読んで強く共感させられたこと、常識をくつがえされたことなどをあげてみる。
『生活習慣病に克つ新常識』
小山内博著 2003年 新潮社/新潮新書 詳しくは...
詳しくは...
『なまけもののマウスからがんになる』
小山内博著 2005年 光文社/知恵の森文庫 詳しくは...
詳しくは...
『企業の現場から19人が語る小山内博の健康づくり』
高木亜由子編 私家版 詳しくは...
詳しくは...
『「水かぶり」でアレルギー知らず!』
小山内博著・高木亜由子編著 2013年 三五館刊 詳しくは...
詳しくは...
小山内博著 2003年 新潮社/新潮新書
『なまけもののマウスからがんになる』
小山内博著 2005年 光文社/知恵の森文庫
『企業の現場から19人が語る小山内博の健康づくり』
高木亜由子編 私家版
『「水かぶり」でアレルギー知らず!』
小山内博著・高木亜由子編著 2013年 三五館刊
常識がくつがえる面白さ

縁結びの愛犬ノエルと。
また、生活習慣病というものを、何万年もかかって形成されたからだと、現代生活との矛盾によって生じたものととらえるのも、理解できた。
そのうえで、健康づくりのために提案された4原則を読むと、それほど違和感なく入ってくる。
まずは「朝食抜き」。
私たちは子どもの時から学校では朝ごはんをちゃんと食べてくるよう指導されてきたし、あらゆるメデイアは、「朝食摂取」は健康の源といっている。脳には朝食=健康とインプットされているから、はじめて聞いたときはびっくりした。
しかし小山内先生は、「朝食摂取」はすすめられないといい、野生の生き物を例にとって諄々と説かれる。
狼やライオンは、お腹ぺこぺこの状態で走り回って狩りをして、やっと餌にありつき、食べ終わってから寝る。活動の前に食べるのではなくて、活動が終わってからゆっくり食べる。それがからだのしくみにかなった食べ方という。いわれてみれば、からだと行動と食べ物の関係は、本来そうかもしれない。
そして林業労働者の調査などを通して、激しい労働の前の「朝食摂取」が胃腸をいかに傷つけるか、データを示して説明される。説得力のある事例だ。
私は朝食はとるが、かなりの早起きで、朝飯前に家事や犬の散歩をすませ、つまり活動をしてから朝食を摂るので、正直ホッとした。小山内理論が朝食をすすめないおもな要因は、「食後すぐに活動すると、消化・吸収を妨げて、胃腸を傷つける」というものだから。
部分的な「水かぶり」でも風邪ひきゼロ
第2の柱「水かぶり」も衝撃的だ。風呂上がりに1分間水をかぶれという。
そのこころは、現代人は冷暖房完備の家に住み、飽食暖衣の生活をしているため、からだがなまって抵抗力が落ちている。そこで「水かぶり」という寒冷の刺激を与えて、副腎皮質ホルモンの分泌を促し、免疫力を強めるという。
「水かぶり」によってアレルギーが改善したという、数多くの事例もあげられ、驚かされた。
私は不眠症や腰痛があるほか、とくに健康に問題はない。ただ、風邪をひきやすく、2カ月に1度くらいは38度以上の熱を出し、咳や鼻水に苦しむのが悩みだった。
それで「水かぶり」をやってみようと思った。
とはいえ、全身浴なんてとてもできない。
風呂上がりおそるおそる手足に水シャワーをかけ、少しずつかける範囲を大きくしていった。まだ全身とはいかないが、「水かぶり」の後、手足がポカポカ暖まってくるのは実感できている。その程度だ。
なのに「水かぶり」をはじめて6カ月。なんと私は1度も風邪をひいていない!
「水かぶり」ってすごいと実感した。
高木さんが今世紀に入ってから1度も風邪をひいていないと自慢するのも、うなずけた。
継続してこその健康づくり
これは週に3回くらい、ゆっくり走って血液循環を良好に維持しようというもの。
よい血液循環は、血圧のコントロールや動脈硬化、がんの予防にもつながるといわれる。
歩くよりも呼吸が弾むくらいの「ゆっくりランニング」のほうが、全身を巡る血液循環の効率がいいとあって、私はノエルとの散歩を、ゆっくり走ることにかえた。といってノエルはオシッコしたり、地面をクンクン嗅ぎまわるので、足踏みすることが多いのだが。
第4の柱「小山内体操」は体幹筋のトレーニングである。これは肩こり・腰痛予防効果が大きいので、是非マスターしたいのだが、まだうまくできない。回数も届かないし、今後の課題である。
といったところで未だ不十分ではあるが、私は小山内式にはまって健康づくりにいそしんでいる。
高木さんは「続けることよ。小山内式は毎日おこなってこそ、不調は改善されるし、健康なからだが維持できる」と励ましてくれる。
そしてパソコンを開いて、当サイトへのある投稿メールを示した。北九州市の女性からのメールで、内容は体操に関する問い合わせだが、次の文が付け加えられていた。
「・・・1昨年より、このサイトで水かぶりを発見して、半信半疑、水かぶりを毎晩するようになって1年、人生最大の悩みであった辛いアトピーがほぼ完治いたしました。気持ちも前向きになり、心から感謝しております
・・・水かぶり健康法が、もっとたくさんのアトピー患者さんに届きますようにと願わずにはいられません・・・」
高木さんはうれしそうに、「こういうメールが来るということは、背後に100人の同じ体験者がいるということなのよ。ゴキブリが1匹出ると、100匹はいるといわれるように」とあまり美しくないたとえを持ち出して、にんまりわらった。
どうやらこうした報告が励みになって、高木さんの活動を支えているようだ。
私もがんばって続けよう。
部分的な「水かぶり」で風邪ひきゼロだから、もう少しあたたかくなって全身「水かぶり」をおこなったら、何が起きるか今から楽しみなことだ。
(文責 高木亜由子)
2018年2月28日
2018年2月28日
●このコーナーに関するご意見、ご質問をお寄せください。
小山内博の健康づくり全般に関するご意見も承ります。
●「トピックス」は、皆様との意見交換の場としたいと思っております。
小山内博の健康づくり全般に関するご意見も承ります。
●「トピックス」は、皆様との意見交換の場としたいと思っております。
