
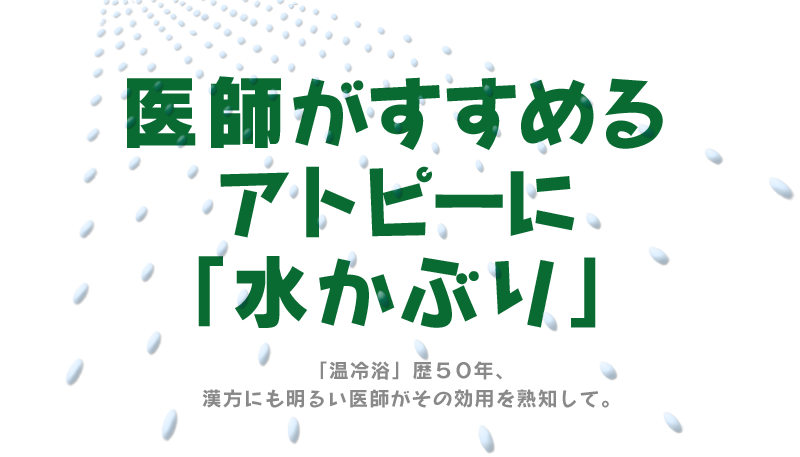
生涯の「健康づくり」に巡り会う
暑くて、厳しい夏でしたが、皆様にはいかがお過ごしでしたか。きっと「水かぶり」で、さわやかに猛暑を乗り越えられたことと推察申しあげます。この夏は、現職の内科医・漢方専門医から、長年「温冷浴」を実践され、その効果を実感しているという、うれしくも心強いメールをいただきました。
小田急線沿線にて開業されている「山内クリニック」の山内浩先生(72)です。
先生は、若い頃は胃腸虚弱体質で、とりわけ夏の暑さに弱く、なんとか丈夫になりたいと健康法を模索した中で巡り会ったのが温冷(交互)浴でした。
以来50年あまり「温冷浴」を実践され、漢方の見地からもその有効性をみとめておられ、患者さんにも適宜すすめておられます。
とくにアトピーの若い患者さんには、皮膚科標準治療や漢方薬とあわせ、温冷浴や風呂上がりの冷水かぶりをすすめて、改善効果を上げておられます。
まずは先生の知見をエッセイ風に綴った「アトピーに対する温冷浴・水かぶりの効用」(『漢方研究』に掲載、改変)を要約してご紹介しましょう。
子どもにも受け継がれて
・・・・私が若かった頃、昭和30年代には「温冷浴」や「水かぶり」などの民間療法がある程度普及していました。その中で私がもっとも気に入ったのが温冷(交互)浴です。
冷たい水槽(18℃〜22℃:季節による)と普通の浴槽(40℃ 〜 43℃)に約1分間ずつ交互につかり、できれば5〜7回ほど繰り返して、最後は水浴で仕上げる(水、湯、水、湯、水、・・・)というものです。
水槽がない場合は、入浴と冷水(水道水)のシャワーを交互に繰り返します。
時間を計るには、1分計の砂時計を利用します。
これが私の真夏の健康法となってから、40年以上たちました。
水浴の爽やかさはなんといったらよいでしょう。この「温冷浴」を済ませた直後は、全身の自律神経系のバランスが回復されるせいか、なんともこころが安らぎます。疲労感が吹き飛んで、真夏の強い陽ざしへの恐怖感もやわらぐのです。
長男には、小さい頃に風邪をひきにくくなるなどと教えて、入浴後の「水かぶり」を習慣づけました。そのせいか、私に似ず元気に成長してくれたものです。本人は医師になってからもこの習慣を続けているようで、うれしい限りです。
私が今日まで元気でやってこられたのも、ひとつは「温冷浴」のおかげともいえましょう。
とはいえ、学生時代は真冬でも水風呂に入って英気を養ったものですが、さすがに近年は風邪をひかない程度の水温(20℃以上)に調整したシャワーを浴びる程度にしています。
ただし、ご高齢の方、高血圧、心臓病、動脈硬化症や重病の方などはお控え下さいね。
冷たい水槽(18℃〜22℃:季節による)と普通の浴槽(40℃ 〜 43℃)に約1分間ずつ交互につかり、できれば5〜7回ほど繰り返して、最後は水浴で仕上げる(水、湯、水、湯、水、・・・)というものです。
水槽がない場合は、入浴と冷水(水道水)のシャワーを交互に繰り返します。
時間を計るには、1分計の砂時計を利用します。
これが私の真夏の健康法となってから、40年以上たちました。
水浴の爽やかさはなんといったらよいでしょう。この「温冷浴」を済ませた直後は、全身の自律神経系のバランスが回復されるせいか、なんともこころが安らぎます。疲労感が吹き飛んで、真夏の強い陽ざしへの恐怖感もやわらぐのです。
長男には、小さい頃に風邪をひきにくくなるなどと教えて、入浴後の「水かぶり」を習慣づけました。そのせいか、私に似ず元気に成長してくれたものです。本人は医師になってからもこの習慣を続けているようで、うれしい限りです。
私が今日まで元気でやってこられたのも、ひとつは「温冷浴」のおかげともいえましょう。
とはいえ、学生時代は真冬でも水風呂に入って英気を養ったものですが、さすがに近年は風邪をひかない程度の水温(20℃以上)に調整したシャワーを浴びる程度にしています。
ただし、ご高齢の方、高血圧、心臓病、動脈硬化症や重病の方などはお控え下さいね。
アトピーは水浴後に痒みが減る
患者さんには、誰にでもすすめるというわけにはいきません。今の人にとっては「水かぶり」はとてもハードルが高いようです。
アトピーの若く元気な患者さんには、症状なり様子をみて、外来診療の合間に食生活の改善事項とともにおすすめしています。
「温冷交互浴」は時間もかかるので、まずは風呂上がりの冷水シャワーでも有効です。
体力のない人(漢方的に虚証のタイプ)では、足元のほうから水をかけて、徐々にならしてゆき、下半身(ヘソや腰から下)、さらには全身(肩から)に及ぶようにすればいいのです。最初は手足と顔の部分にだけ、水をかけて慣らしてゆくのもよいでしょう。
冷たくて我慢できない人は、ふたたび湯につかって十分温まってから、再度、適温(20℃以上でよい)にした水をかぶります。これを何度か繰り返すと「温冷交互浴」になり、からだがポカポカしてきます。
いずれの場合も、最後は水で締めます。
ただし、寒さに弱く、震えがくるような人は、温浴で仕上げてもよい(湯、水、湯、水、湯、など)と思います。決して無理をなさってはいけません。 ここで入浴後の「水かぶり」あるいは「温冷交互浴」の効用をあげておきましょう。
★ 温冷の交互刺激によって肌をひきしめ、熱をさます
★ 自律神経系のバランスが回復され、こころが安らぐ
★ 内因性のステロイド分泌を高め、免疫力が増す
★ 温浴だけでは痒みが増すが、水浴後は痒みが減る
★ ストレスが発散され、気分爽快になる
★ 皮膚呼吸がさかんになり、薄着に慣れ、かぜをひきにくくなる
アトピーの患者さんは、温浴だけで風呂から上がると、炎症の強い時期では赤みと痒みは増強しがちです。冷たい水をかけて、熱と寒とのバランスをとることは、おそらく合理的だと思います。
アトピーの東洋医学的な病態には、諸説ありますが、私には湿熱(しつねつ)、血熱(けつねつ)などといわれる熱(炎症)が重い状態と、肝鬱(かんうつ。心理的ストレスがたまって発散されないことによる諸症状)、脾虚(ひきょ。胃腸の消化、吸収や水分代謝の働きが低下した状態など)の要因が大きいと思われるのです。
したがって、「温冷浴」や風呂上がりの「冷水かぶり」を積極的に取り入れて、熱をさまし、たまったストレスを発散し、気分爽快にすることが有効と考えられます。
日常的に「温冷浴」や「水かぶり」を実践されて、そのうえで必要に応じたステロイド外用剤(軟膏類)、保湿剤などによるスキンケアをされ、さらに体質に合った漢方薬を服用していただければ、より効果的でありましょう。
アトピーの若く元気な患者さんには、症状なり様子をみて、外来診療の合間に食生活の改善事項とともにおすすめしています。
「温冷交互浴」は時間もかかるので、まずは風呂上がりの冷水シャワーでも有効です。
体力のない人(漢方的に虚証のタイプ)では、足元のほうから水をかけて、徐々にならしてゆき、下半身(ヘソや腰から下)、さらには全身(肩から)に及ぶようにすればいいのです。最初は手足と顔の部分にだけ、水をかけて慣らしてゆくのもよいでしょう。
冷たくて我慢できない人は、ふたたび湯につかって十分温まってから、再度、適温(20℃以上でよい)にした水をかぶります。これを何度か繰り返すと「温冷交互浴」になり、からだがポカポカしてきます。
いずれの場合も、最後は水で締めます。
ただし、寒さに弱く、震えがくるような人は、温浴で仕上げてもよい(湯、水、湯、水、湯、など)と思います。決して無理をなさってはいけません。 ここで入浴後の「水かぶり」あるいは「温冷交互浴」の効用をあげておきましょう。
★ 温冷の交互刺激によって肌をひきしめ、熱をさます
★ 自律神経系のバランスが回復され、こころが安らぐ
★ 内因性のステロイド分泌を高め、免疫力が増す
★ 温浴だけでは痒みが増すが、水浴後は痒みが減る
★ ストレスが発散され、気分爽快になる
★ 皮膚呼吸がさかんになり、薄着に慣れ、かぜをひきにくくなる
アトピーの患者さんは、温浴だけで風呂から上がると、炎症の強い時期では赤みと痒みは増強しがちです。冷たい水をかけて、熱と寒とのバランスをとることは、おそらく合理的だと思います。
アトピーの東洋医学的な病態には、諸説ありますが、私には湿熱(しつねつ)、血熱(けつねつ)などといわれる熱(炎症)が重い状態と、肝鬱(かんうつ。心理的ストレスがたまって発散されないことによる諸症状)、脾虚(ひきょ。胃腸の消化、吸収や水分代謝の働きが低下した状態など)の要因が大きいと思われるのです。
したがって、「温冷浴」や風呂上がりの「冷水かぶり」を積極的に取り入れて、熱をさまし、たまったストレスを発散し、気分爽快にすることが有効と考えられます。
日常的に「温冷浴」や「水かぶり」を実践されて、そのうえで必要に応じたステロイド外用剤(軟膏類)、保湿剤などによるスキンケアをされ、さらに体質に合った漢方薬を服用していただければ、より効果的でありましょう。
日本の内科医の父がみとめていた「冷水養生法」
若い頃から「温冷浴」を実践され、その効用を熟知されたうえで治療に役立てようとされる。さらに漢方も学ばれて、西洋医学を補完され、全体的に人間を診ようとする姿勢に深い信頼感を覚えます。今日、医薬以外の健康法を積極的にすすめる医師はあまり見かけませんが、じつは、「冷水浴」は日本医学の父とも呼ばれる医師佐々木政吉が、明治30年代に国民の健康増強策としてつよく普及につとめていたという歴史があります。
佐々木政吉は安政2年(1855年)生まれ、東京帝国大学医学部に入学し、ドイツに留学。帰国して同大学医学部に日本人初の内科学教授として就任、日本人2番目の医学博士となる。
まさに日本内科医のルーツともいうべき医師で、日本の内科は佐々木政吉から始まり、現在全国で活躍中の内科医は、みな彼の弟子、孫弟子、ひ孫弟子ということになるのです。
その政吉がドイツ留学中に「冷水浴」を体験し、その卓効を認めて、帰国してから「冷水養生法」として広く普及につとめたのです。
東京帝国大学でも講演し、それを聴いた夏目漱石が「冷水浴」を実践していたという記録もあります。(「新発見!夏目漱石も冷水浴を行っていた!」2014年3月23日掲載記事を参照)
「冷水養生法」の効用は、山内先生が挙げたものとほぼ同じです。
山内先生は、日本医学のオーソリテイの正当な継承者というべきでしょうか。
山内 浩(やまうちひろし)●プロフィル
●1972年信州大学医学部卒業
●同第2内科研修医、慶応義塾大学大学院、国立栃木病院内科医長、都立大久保病院東洋医学科初代医長、つるかめ漢方センター所長などを経て2007年開業
●日本東洋医学会認定漢方専門医、指導医。肝臓専門医、消化器病専門医
●著書に『アトピー性皮膚炎の漢方治療』など多数
● URL:http://www.yamauchi-cli.com/
(文責 高木亜由子)
2017年8月31日
2017年8月31日
●このコーナーに関するご意見、ご質問をお寄せください。
小山内博の健康づくり全般に関するご意見も承ります。
●「トピックス」は、皆様との意見交換の場としたいと思っております。
