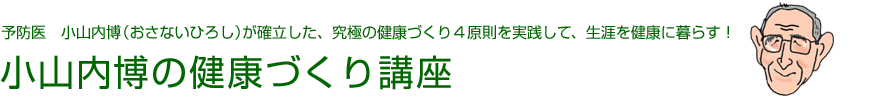
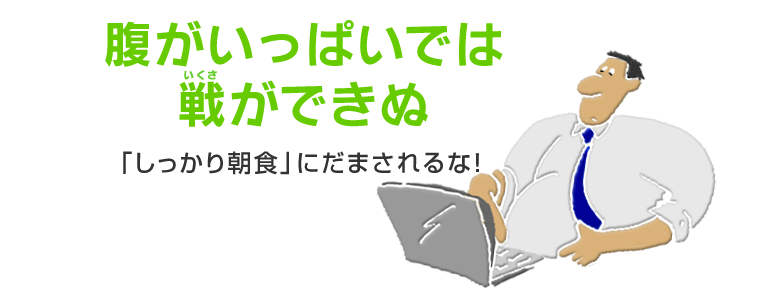
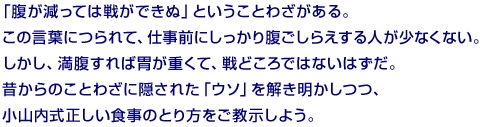
「しっかり朝食」は逆効果
朝からしっかり食べて仕事をしようと、外食産業が朝食に客を呼び込んでいる。駅なかや通勤街では、朝早くから回転寿司やラーメン店、カレーハウスなどが営業し、サラリーマン風の客でけっこうな入りだ。
不況のあおりを受けた外食産業が、朝食に目を向けはじめたらしい。
しかしちょっと待ってほしい。
朝からしっかり食べたら、仕事になるだろうか。おなかがいっぱいになれば、動きが鈍くなるし、頭も働かなくなって、へたをすると眠くなってしまう。
からだはそのようにできているのだ。
ものを食べれば消化吸収がはじまり、胃や腸をはじめとする消化器官がいっせいに働き出す。目には見えないけれど、からだはその仕事で大忙しなのだ。
それなのに、これからばりばり働こうというのでは、消化吸収ばかりか実際の仕事にも悪影響を及ぼす。
からだは2つの仕事を同時に、完璧にはできないのだ。
簡単に説明しよう。
血液は活動する部位へと酸素と栄養を運ぶ。ものを食べると消化活動が始まって、血液は胃腸に集まる。そうなると、脳や筋肉にまわる血液は減ってしまう。少なく配分された血液では、十分な仕事ができるとはいえない。消化活動のほうも、脳や筋肉に血液を横取りされてしまい、不十分なものになってしまう。
というわけで、「しっかり朝食」は、からだにとっても仕事にとってもプラスにはならない。
それでもしっかり朝食をとりたい人は、食休みをとるしかない。食後ゆっくり休むなら、からだは100%消化吸収に専念できるから、問題は起きない。
とくに筋肉を使う人は、食後すぐの労働は胃腸にダメージを与えるので、何があっても食休みをとってほしい。
小山内医学探偵の推理にナットク
「腹が減っては戦ができぬ」は真っ赤なウソというわけだが、このことわざ、昔から言い伝えられている。昔からの言い伝えだから正しいと思い込んで、仕事前にしっかり食べる人は少なくないだろう。その影響ははかりしれない。
このように誤ったことわざは、いったいいつどこで生まれたのだろうか。
小山内氏は、その故事来歴を読み解いている。
ほかにも、食べることに関して「食べてすぐ寝ると牛になる」ということわざがある。さらに「親が死んでも食休み」という言い伝えもある。
これらのことわざないし言い伝えは、相互に関連しているので、小山内医学探偵(!)と一緒に謎解きをしよう。(『生活習慣病に克つ新常識 まずは朝食を抜く!』より要約)
これらの言い伝えが生まれたのは、農耕時代と考えられる。
狩猟時代から農耕時代に移行すると、支配、被支配の関係が生じるようになり、租・庸・調といった、今でいう税金のようなかたちで収奪が行なわれるようになった。
庸というのは、“時々出てきて、ただで働け”ということで、役務の無料提供である。
使われる側は、自分のために働くわけではないから、ばかばかしくなって、“腹が減って働けない”とごねる。
使う側は、それではしかたなく“食べさせるから働け”といって食べさせると、からだは食べたら眠くなるから、寝てしまう。
使う側は、せっかく働かせようと思ったのに困ったことになり、“飯を食べてすぐに寝ると牛になるぞ”といっておどして対抗しなければならなくなった。
というのが真相らしい。
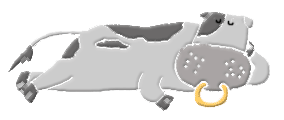
「食べてすぐ寝ると牛になる」というのは、他人にものを食べさせて働かせる支配者のいい分。「腹が減っては戦ができぬ」は被支配者のいい分。
「親が死んでも食休み」は、食後は眠くなるのに、無理をして休まないとからだをこわしますよという、おそらくは庶民の間に伝えられた教訓で、これだけが真実のからだの言い分ということになる。
このような時代背景から生まれた言い伝えが、今日まで生き残り、人々を束縛していることに驚かされる。
小山内氏は、同書の中で、「・・・これに限らず昔からの言い伝えやことわざには、それぞれの立場で都合のいい言い分や主張も多く含まれているので、盲信してはいけません」と警告している。
朝食を食べるとふとる
“しっかり”でなくとも、朝食はとらなくてはいけないと信じている人は多い。朝食こそ1日の活力源。朝食抜きでは、ガス欠で、力がはいらないという。
しかし、これも思い込みに過ぎない。
朝起きたとき、からだはからっぽではない。
前夜飲み食いした食事が、寝ている間に消化吸収されて、各栄養素は必要な場所に行き、活動の主体となるブドウ糖は、筋肉や肝臓にグリコーゲンのかたちでしっかり蓄えられている。
寝ている間は、身体活動はほぼ休止状態にあるから、蓄えはほとんど減っていない。消費するのは基礎代謝だけである
朝は、何も食べなくともエネルギー満タン、活動の準備は十分ととのえられているのである。
それなのに、「腹が減っては・・・」とばかりパンやご飯を食べてしまうと、どうなるだろうか。
消化吸収されたブドウ糖は、1部は午前中の活動に使われるが、余った分は、筋肉や肝臓はすでに前夜の分が蓄えられて満杯なので、脂肪に変えて蓄えられる。
朝起きてすぐ、エネルギーを使うことなく食べてしまうと、ブドウ糖は脂肪になって溜め込まれるわけだ。
昼食も食べるとなると、朝と昼は食間が短いため、備蓄した脂肪エネルギーはあまり使われず、ブドウ糖はさらに脂肪に変えて溜め込まれる。
こうして朝も昼もとると、脂肪細胞は肥大するいっぽうということになる。
一般的に3食はしっかりとるようにいわれるが、今の平均的日本人の運動量からすれば、量にもよるが、1日3食はとりすぎではないだろうか。
小山内氏は、3食の習慣についても歴史をひもといている。(『生活習慣病に克つ新常識 まずは朝食を抜く!』より抜粋)
「・・・庶民に1日3食が定着したのは、明治になってからのこと。時の政府が平民を集めて軍隊を作り、腹いっぱい食べられるようにと武士階級と同じ1日3食を採用したことから、全国的に普及した。・・・食うや食わずの時代に制度化した食習慣を、健康の源のように思い込み、食べ物が余っている時代にも守り続けているのでは、からだに矛盾を生じるのは当然・・・」とわらっている。
ふとりたくないなら、朝食は抜くのが正解のようだ。
午前中は備蓄した脂肪エネルギーを使って活動し、消費して、さらなる脂肪の預金をつくらないことである。
胃腸を守り、肥満を防ぐ食事のとり方とは
今の時代はさまざまな健康情報が満ちあふれ、うっかりのせられると健康をそこねることになりかねない。小山内氏は、予防医学の立場から、からだの決まりにかなった健康づくりを指導されてきた。小山内式4原則は、どれも生理学からみてまことに理にかなった健康法である。
朝食をやめよというのも、朝はこれから活動が始まるので、食後すぐの活動は消化によろしくないから控えなさいということだ。朝食がわるいわけではない。
からだのしくみは、活動のあと食事、食後はゆっくり休むようにできている。
昼食もたらふく食べれば、午後の仕事にかかる頃に睡魔が訪れ、仕事に影響すると警告する。
小山内氏のいた労働科学研究所の調査によると、工場などの労働災害は、昼食後まもなくの午後2時ころにもっとも多く発生するという。
食後、腹ごなしなどと称してバドミントンやキャッチボールなどをするのも、消化を防げ、胃腸をキズつけるもとになる。
それこそ食後は 「親が死んでも食休み」である。
小山内氏のすすめる、からだの決まりにあった食事のとり方とは−−−−
朝食はとらず、昼食は軽めに、日中はできるだけ空腹状態で活動して、あとは寝るだけの夜にしっかりした食事をとる。そうして夜の間に栄養を溜め込んで脂肪にして蓄え、日中は備蓄した脂肪エネルギーを使って活動する−−−− というものである。
正しい食事のとり方と順序を守ることによって、胃腸を守り、肥満を防ぐことが可能だ。
(文責 高木亜由子)
2016年6月30日
2016年6月30日
![]()
・ 4原則のいずれか、あるいはすべてを実践し、どれくらいの期間で、どのような変化がみられたか
・ 症状のある場合は、改善されたかどうか
・ その他、どんなことでも気づいたことをご報告いただければ、幸いです。
・ お名前はイニシアルでもけっこうです。
・ 掲載に際しては、ご連絡申し上げます。
皆様の体験が、きっと同じような問題を抱えた方の役に立つと思いますので、どうかふるってご投稿ください。
小山内式健康づくりの詳細は、 『生活習慣病に克つ新常識 まずは朝食を抜く!』『なまけもののマウスからがんになる』などの著書をお読みください。
●このコーナーに関するご意見、ご質問をお寄せください。
小山内博の健康づくり全般に関するご意見も承ります。
●「トピックス」は、皆様との意見交換の場としたいと思っております。