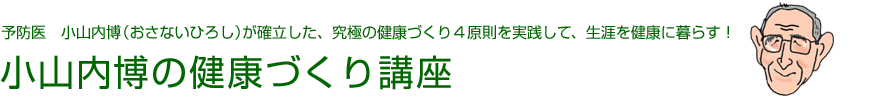


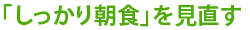
とりわけ、きちんと朝食をとることが大切とされ、文部科学省では「早寝早起き朝ごはん」を実践する国民運動を展開しているほどだ。
その背景には、子供たちの食生活の乱れがある。朝食といえばスナック菓子を与えるだけという家庭も多い中、「しっかり朝食を」という声が起きるのも、わからなくない。
しかし、「しっかり朝食を」とることが、ほんとうに子供の心身にとってプラスになるのだろうか。
朝起きて食欲もないのに朝食を強要され、登校拒否になったり、朝食後すぐの運動で、おなかの調子を崩す子供も多いと聞く。
小山内氏は、食後すぐの活動は、消化を妨げるので、好ましくないと指摘された。
ここではちょっと視点を変えて、摂取より消化吸収の面から、1日の活動が始まる朝に「しっかり朝食を」とることの是非を、問い直してみたい。
食後すぐの運動がアレルギーを誘発する
ちょっとコワイ話をしよう。アレルギーを持つ子が、食後すぐにマラソンなどの激しい運動をすると、ひどいじんましんを発生したり、呼吸困難に陥ったり、血圧低下、意識障害など、アレルギーよりひどいアナフィラキシー様症状を呈すことがある。
食物依存性運動誘発アナフィラキシー症候群と呼ばれ、全国の学童に多くみられるとの報告がある。
なぜこのような症状が起きるのか、小山内氏は著書『本当はヤセたいのに、まだ朝食を食べている人たちへ』の中でつぎのように述べている。
 「食後すぐマラソンのような激しい運動をすれば、血液は筋肉へ集中する。そうなると消化吸収のために胃腸に配分される血液は手薄となり、消化活動は不十分なものとなってしまう。その結果、たんぱく質は消化不良のまま小腸に送られ、十分に分解されることなく吸収されることになり、食物アレルギーが起きる」と。
「食後すぐマラソンのような激しい運動をすれば、血液は筋肉へ集中する。そうなると消化吸収のために胃腸に配分される血液は手薄となり、消化活動は不十分なものとなってしまう。その結果、たんぱく質は消化不良のまま小腸に送られ、十分に分解されることなく吸収されることになり、食物アレルギーが起きる」と。食物アレルギーは、たんぱく質の分解が不十分なかたちで吸収されることから起きる現象であることはよく知られている。
小山内氏は、食後すぐの激しい運動が、アレルギーを誘発するという因果関係をいち早く見抜き、食べてすぐあと、胃腸が消化活動の真っ最中にあるときに運動するのは控えるよう警鐘を鳴らしていた。
朝食をとった子供に腸カタルが多い
このような症状は、アレルギーを持つ子供にだけみられるのではない。ふだんからおなかの様子の悪い子も、食べてすぐに運動すると、倒れたり、全身倦怠などの症状を示すことがあるという。
小山内氏は、夏になると小中学生が朝礼で倒れる「起立障害」が問題になった時に、当地の小中学生120人のおなかを診察したことがある。(『生活習慣病に克つ新常識ーまずは朝食を抜く!』より)
当時関係者の間では、朝礼で倒れるのは「朝ごはんを食べてこないから(腹ペコで倒れた)」といわれたものだが、原因は腸カタル(腸の粘膜が炎症を起こして下痢をする病気)だった。
小山内氏が倒れた子のおへその脇の太陽神経叢という個所を押さえると、強い圧痛があることから、潜在的にあった腸カタルが悪化して、長時間の起立に耐えられずに脳貧血で倒れたということが判明した。
その子たちはほとんど全員朝食をとっていたという。
朝食をとらない子よりとっていた子に多く腸カタルがみられたのである。
おそらく朝食をとっていた子らは、ふだんから食後すぐの勉強や運動で、消化が不十分なために、腸の様子が悪く、慢性的に腸カタル気味であったと思われる。
食べてすぐ走ると、わき腹が痛くなることからも、消化中の運動はおなかによくないことがわかる。
小中学生120人のうち、潜在的な腸カタルを持っている子は約3割いたという。
消化不良が腸内戦争をひき起こす
腸カタルは食事のとり方と大きく関係している。食べ物を急いでかきこんだり、食後すぐに運動したりすると、消化液の胃酸が間に合わなくて、消化が十分にされない。そうなると、食べ物の中に混入した菌が殺されることなく腸へ送り込まれる。
胃酸は強い塩酸で、たんぱく質の消化を手助けするとともに、胃内に入ってきた菌を殺す役目を持っている。その殺し屋が力不足で、菌は殺されることなくやすやすと腸に到達してしまう。 腸の中には、ビフィイズ菌などの善玉菌や悪玉菌が常時100種類くらい棲みついている。それぞれは勢力を競い合ってバランスを保っている。
そこへ殺されずに入ってきた新しい菌が加わると、バランスが崩れて腸内戦争がはじまる。
これが腸カタルだ。
腸内戦争が小腸から大腸に波及すると、下痢となる。
食べ過ぎると下痢をするのは、消化液の分泌が間に合わなくて、生き延びた菌が腸内戦争を引き起こした結果である。
他にも腸カタルはいろいろな悪さをする。
菌の中には、有害な物質を作り出すものがあり、その毒素が腸から吸収されて、中毒症状を呈することもある。
食欲がなくなってだるいといった程度から、高熱を出して寝込んだり、激しい下痢に悩まされたり、あるいは頭痛や吐き気、めまいを起こすこともある。運動中に気分が悪くなって座り込むようなこともあり、朝礼時の「起立障害」にもつながる。
腸カタルの子供は食中毒にもかかりやすい。
O−157のような菌にもすぐ負けてしまう。
もし腸内菌のバランスがよければ、O−157も昔から腸内に棲んでいる常在菌のひとつだから、トラブルを起こすことなく共生できるはずだという。
ゆっくり食べて、おなかの調子をととのえる
腸カタルや食中毒から身を守るためには、ふだんから腸内菌のバランスを保っておくことが大切だ。そのためには、食べるものだけでなく、食べたものがきちんと消化吸収されるかどうかに気をつかいたい。小山内氏は次のように提言される。(『生活習慣病に克つ新常識』より)
「いくら気をつけていても口からはいろいろなものが入ってくる。予防するには、ふだんから腸内菌のバランスをよくしておいて、入ってきた菌は胃の塩酸とペプシンでほとんど殺されるか、弱くされて腸に送り込まれ、腸に棲んでいる善玉菌と戦わせて押さえ込むという、からだの絶妙な働きにまかせるに限る」。
 そのためには、朝食摂取の習慣も見直す必要があるという。
そのためには、朝食摂取の習慣も見直す必要があるという。「朝、食欲もないのに無理に食べさせても、消化吸収が十分にされなければ栄養は身につかない。急いで食べれば胃酸の分泌が間に合わなくて、いつもおなかの調子が悪いことになる。
それでは、子供がかわいそう。
なにも朝の忙しい時に食事をとらなくても、栄養失調にはならない。それよりゆっくり食べて(給食時などに)、食休みもとれるようにしたほうが、栄養の吸収もはるかに効率的。そうして腸内菌のバランスをいい状態に保って、ふだんからおなかの調子をととのえてあげるように」と。
「朝食信仰」から解放される
子供に聞くと、朝は眠いし食べたくないという声が多い。勉強や塾通い、ゲーム遊びなどで、全般に夜が遅くなっているのだろう。
昔のように、早起きして家事を手伝ったり運動でもすれば、食欲が湧くかもしれないが、起きてすぐ食べたくないのは、自然なことに思われる。
子供にもいろいろな生活があり、必ずしも理想的な「早寝早起き朝ごはん」が望めないのであれば、「朝ごはん」のみを強要するのは無理があるのではないだろうか。
からだが欲していなければ、消化液の分泌も十分でないし、無理に食べさせれば、これまでみてきた通り、消化吸収の面から悪い影響を及ぼす。
まして、朝食をとらないと「からだが目覚めない」「ブドウ糖が不足して脳が働かない」などと脅し、テストの成績も、朝食をとった子供ととらない子供を比較して、朝食をとった子供のほうがいいと決めつけたりするのは、誤解を招きかねない。(読売新聞「食育の現場」より 2010/4/15)
どんな条件下で比較したのかわからないが、物を食べると眠くなるから、テストの結果はむしろ逆ではないだろうか。勉強の前に、たらふく食べたりすれば、消化のために血液は脳からも去り、胃腸にまわって、まぶたは重くなり睡魔に襲われる。からだのキレも悪くなり、鈍くなるのはだれにでも覚えがあるだろう。
これはふだんの食習慣もあるから、いちがいにはいえないが、ともかく朝食と成績を結びつけて論じるのは、親を惑わしかねない。
食事の手抜きやしつけの問題は、「朝食摂取」とは別個に論じられなくてはならない。
元大阪日本赤十字病院医師井上敬氏(生命哲学研究所)によれば、日本は「朝食真理教」の国であり、「朝食をしっかり」などと国をあげて奨励する国は、世界中で日本だけという。
朝食をとるなら、なるべく消化の負担にならないものを。運動の前なら、飲み物くらいにしておいたほうがからだのためである。
(文責 高木亜由子)
2010年5月7日
2010年5月7日
●このコーナーに関するご意見、ご質問をお寄せください。
小山内博の健康づくり全般に関するご意見も承ります。
●「トピックス」は、皆様との意見交換の場としたいと思っております。